こんにちは。心理カウンセラーの熊倉瞳心帆(くまくらみさほ)です。
みなさんはお子さんを「褒めて伸ばそう」「褒めることでいい子になる」と考えて、とにかく褒めまくる子育てをしていませんか?
本当に「褒めて伸ばす」ことでお子さんはすくすく育つのでしょうか?
そして褒められて育ったお子さんは、大人になって幸せな幼少時代だったと感じるのでしょうか?
今日は実際私の子育て方法での成功したこと、失敗したことのほか、成人した息子の当時の感情を聞いたことをお伝えしていこうと思います。
褒めて伸ばす育児とは?

子育てするのによく「子供は褒めることで伸びる」「褒めて伸ばす子育て」を推奨している書籍や口コミ(子育てサイトなどで)があります。
確かに「〇〇できないなんて、ダメな子ね」とか「〇〇ちゃんはできるのに、あなたはなんでできないの?」などと言われ続けていた結果、自分に自信がなくなり、自己肯定感が低く成長してしまったアダルトチルドレン気質のかたは、自分は子育てでそうはならないようにしよう!と、褒めるようにしていると思います。
ただ、最近は褒められてばかりの子育てはかえってお子さんがプレッシャーに感じてしまうといったデータが報告されています。
褒めて伸ばす育児で育てられたメリット・デメリット
「褒めて伸ばす」ことがいい子育てだと書籍等で証明されていて、自信を持って育児していたかたには大変ショックなデータかもしれません。
ここで褒められて育ったことによるメリットとデメリットをご紹介します。
【メリット】
① 自信を培うことができ、自己肯定感があがる
② 失敗を恐れず挑戦し続けることができる
③ 挑戦することのリスクを恐れず、ポジティブな心構えで取り掛かることができる
④ 親との信頼関係がアップする
以上のメリットを考えると、やはり褒めて伸ばすことが子供の成長にとてもいい影響を与えるのでは、と思いますね
一方で、デメリットもありますので、ご紹介します。
【デメリット】
① 褒められることが当たり前という状況になり、他人の評価を気にして褒められない場合ストレスに感じ打たれ弱くなる
② 褒められることでモチベーションをあげていたので、自らモチベーションを上げることが難しくなる
③ 褒められることで、親が自分を認めてくれると感じ、「もし失敗したら?」「テストで悪い点を取ったら」親から見捨てられるのではないかとストレスを感じる
④ 褒められるように行動を続けていることで、本当の自分を隠しやすくなる
⑤ 「褒められる」ことが目的となり、難解な課題、挑戦を避けようとする
⑥ 褒められ続けることで「自分は正しい」と思い込むようになってしまい、他人の意見を無視したり、自分の間違いを認めなくなってしまう
このようにお子さんは親の喜ぶ姿を見たいと一生懸命行動します。
親が褒めて伸ばす育児を意識して実践していることは、お子さんは「親がわざと褒めている」ことを察知することができています。
そして親が自分のことを本当に褒めているのか、自分自身が好きなのか/できる自分だから好きなのかと不安になり、虚しさを感じる可能性があるのです。
また自己肯定感があがる、ポジティブな姿勢という点はとても理想的ですが、逆に自分勝手やわがままと捉えられ、社会に対する適応力を身につけることが難しくなってしまう可能性もあります。
成長に役立つ声かけはズバリ・・・
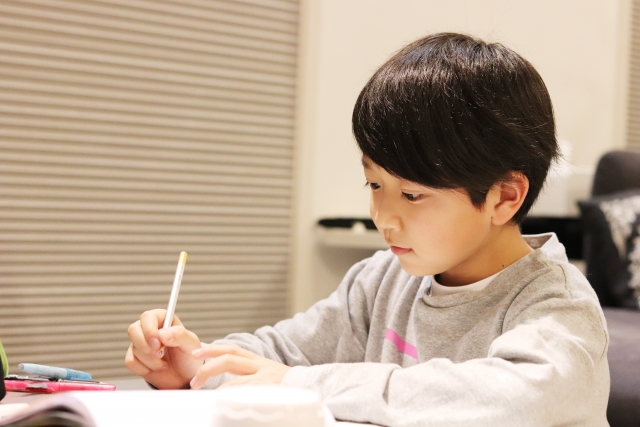
褒めて伸ばす教育はいい点もありますが、褒めすぎるとかえってわざとらしくなってしまう、そのバランスがとても重要です。
そこでお子さんの成長につながる声かけは、ズバリ「認める」ことです。
例えば
・宿題を自分から取り掛かれたのすごいね
・漢字練習、丁寧に字が書けてるね
・〇〇手伝ってくれたの、ママとても助かったよ
など、お子さんが取り組んでいること自体を認めたり、褒めたりすることです。
テストで何点だったから褒めるとか責めるとかでなく、テストを頑張った結果、間違えた箇所はどうして間違えたのかをお子さんが理解できているか?をしっかりと聞き取ることで、お子さんはたとえ悪い点数であっても怒られない、といった安心感を持つことができます。
我が家の子育て中の会話失敗談💦
我が家の息子が小学生の頃、将来のなりたい職業で「お笑い芸人」といったことがありました。
小学生の男子あるあるですね(笑)
そんな時、わたしは心の中では「嫌だな。なれっこないのに」と考えていました。
でも頭ごなしに「なれっこないよ」とダメ出しをせず・・・
「たとえばどんなギャグとかがあるの?」と聞いてみました。
息子は当時流行っていた芸人さんのギャグを得意げに披露します。
そこで私が「それってパクリじゃないの?」といったところ
息子は痛いところを突かれた〜といって、芸人への道を諦めました。
諦めたというより忘れて次の興味のあることに気持ちが移ったという方が正しいかもしれません。
これは否定したわけではありませんが、息子の将来を認めて応援したことにはなりませんね。
また大学進学の際、高校2年生の3者面談では
「将来が全く考えられないから、ママ決めて」
というまさかの発言。私がなって欲しい職業に就くというのです。
息子もアダルトチルドレン気質かHSP気質があるので、自己主張をしないのです。
当時は進学するために、とりあえず臨床工学技士を勧めてみて、大学も工学部に進学しました。
ところが、大学進学と同時にコロナ流行。初めての一人暮らしと訳のわからないままオンライン授業。友達もできず、コロナ鬱に陥り大学内のスクールカウンセリングを受けるうちに、自分の将来も考えることになったようです。
そして大学4年生に進級する際に、本人から将来の希望について相談されることになりました。
私は小学生以来息子自身から将来について相談されることで、真剣に聴き、一緒に考えました。
その上で、学部の変更と大学生活の延長、学費の援助を承諾し応援することを伝えました。
このことが後に息子から、「親が真剣に聴いてくれた。応援してくれる」という安心感と責任感につながったと、嬉しい言葉をもらえました。
今日からできる心地よい声かけ

褒めて伸ばす教育のデメリットばかりではないので、本当に褒める時はしっかりと褒めましょう。
褒められることはやはり嬉しいものです。
そして、日常では褒めるばかりではなく、「認める」ことを心がけるようにしましょう。
・自分で考えたことを認める
・お手伝いしたら、家族の一員として認める
・やるべきこと、決まりを守ることはお子さんが納得できるようにしっかりと伝える
・他人と比べない。その子自身ができること、できたことを認める(褒める)
いかがですか?褒めるより認める言葉で、お子さんの不安を取り除き、行動できるようになるのです。
そして自己肯定感も上がり、自分で物事を考え実行できる力を身につけることができます。
親の立ち位置としては、上からでなく伴奏者として応援する育児をして、お子さんの成長を楽しむようにしてみるのはいかがでしょうか?
お子さんとの関わり方についてお悩みがある方。
カウンセラーと一緒に声かけ方法や距離感についても考えてみませんか?
幼少期の声かけ、青年期の声かけは変わってきます。
お子さんの成長に合わせた声かけについてもご相談いただけます。
良かったら一度私にご相談ください。
初回お試しカウンセリング60分1000円でご相談受付中です。



